富世遺跡とは
富世遺跡は、かつて「太魯閣遺跡」と呼ばれていて三級古跡に指定されている先史時代の遺跡です。花蓮にロングステイ、ミドルステイした場合、まず訪れるであろう太魯閣渓谷の入口に位置する遺跡です。
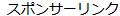
富世の旧称は「富世岡」であり、「歩哨(ほしょう)停」又は「歩哨所」の意味を持っています。
その昔、泰雅族(タイヤル族)の人々がここで耕作していた際、平地の原住民からの襲撃に頻繁に遭っていました。
そのためのバリケードを設置したのが名前の由来だそうで、初めは「不備尚」と呼ばれ、後に「富世岡」に変わり、民国35年に「富世」に改称したようです。
富世遺跡はまるで弧を描いた月のような地形であり、長さ約300メートル、広さは約30~50メートルの規模から成り、立霧渓河口にある太魯閣国家公園の牌坊(パイ ファン、チャイニーズの伝統的建築様式のモニュメンタルなアーチ形の門、又は門構えの一つであり、日本でも中華街などで見ることができる鳥居の様なもの)の前方約100メートル付近の河岸段丘に位置しています。
段丘の南端は険しい岩壁で、新城山の南麓であり、北側は立霧渓河口、東北側は太平洋に面し、西側は太魯閣口となっています。
富世遺跡の考古学的価値
富世遺跡は、背後に山、前方に海という厳しい条件にも関わらず原始の風貌を今も保っているという非常に貴重な存在です。
考古学者たちが初めてこの河岸段丘を訪れた時、85個の地表に規則正しく配列された単一の石、そして所々に石が塔状に積み重ねられている状態だったようです。その中の塔状の石の1つの中から一塊の石柱が発見されました。
この石柱の先端部には、人工的に柱になるように磨かれた痕跡がはっきりとあったようです。
その形状は、台湾東部の「巨石文化」の中の「単石」との共通点が非常に多く、卑南文化と同じく新石器時代の文化の産物である事が判明していったんですね。
富世遺跡の単石と石板棺は混合して出現しており、2種類の文化がお互いに結合した結果である、いう事がはっきりと見出せるようです。
その他、富世遺跡にて採用が判明している屈肢葬(体を曲げて埋葬する)の埋葬方式は西暦前の北部の「十三行文化」の側身屈肢葬(体を曲げて横にして埋葬する)のスタイルと非常に類似しているという事実も判明。
この遺跡は発見当時、台湾考古学の中に何の記録もなかったため、考古学界の処女地とされ、学者達を大いに雀躍させたようです。
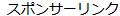



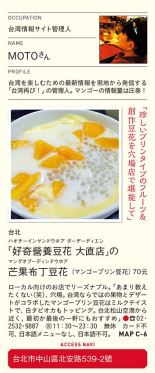
 アイリン。
アイリン。

